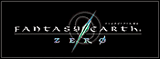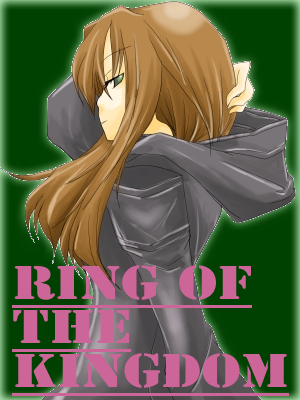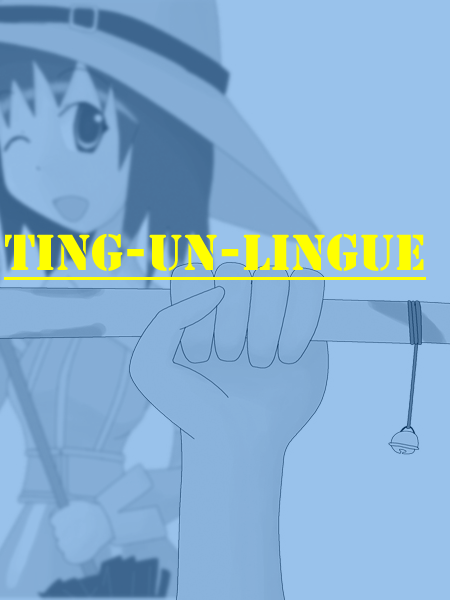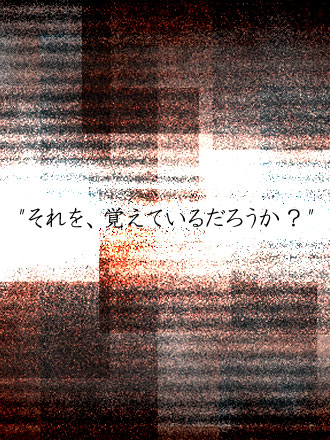About "AT通信"
- FEZ内であまり役に立たない情報を、自分達が楽しみながら発信していく「組織」、またはその「情報媒体」です。
POWER PUSH EVENT
PICK UP
NOVEL
「浦波」---著[ディガル]---画[ラフラ。]---
第一項
----「浦波」
漫々たる海上、大風に波の逆巻き、打てば返し、返しては打つが如く、波の揉み合う景色を業にたとえて浦波という。
---正伝新陰流
激烈な敵軍の攻勢に、味方は総崩れになっていた。
響くのは敵軍の喚声のみ。味方は押され、逃げまどう。
俺は必死に周囲を叱咤し、崩れる戦線を維持しようとするが、誰もそれに応えず、俺と俺の所属する小隊の人間だけが残る。
攻め寄せる敵軍、俺は立ち向かう。小隊の魔法使いも、弓も、斧を抱えた戦士も、健気に着いて来る。多勢に無勢だというのに。
俺はやみくもに前へ進もうとして、激しい魔法攻撃の嵐に晒された。
いくつかの攻撃が、鎧を凍てつかせ、動けなくなる。弓も降り注ぎ、後ろで立ち往生する味方たち。俺は助けにも行けずに立ちすくむ。
そして、真っ白な光の矢が俺を射貫き、俺だけを崖下に叩き落とす。
俺が刀を咥えて両手で崖を這い上がったのは、それより数刻後。
さっきまでの激戦地に立った俺を迎えたのは、変わり果てた姿になった小隊員たちだった。踏みにじられ、原型をとどめていない彼らの姿を見て、俺は叫び声をあげた・・・
・・・俺は自分の叫び声で目を覚ました。
深山幽谷というに相応しい、森の奥。近くで滝の水音が聞こえる以外には、人の立てる物音が何もない場所。
前の戦闘で、小隊員を全て失い、おめおめと生き長らえた俺。
自分の武には自信があったが、自らの武で何一つ守れなかった。
だが刀を操るものとして、それを研鑽する以外に何一つできることはなく、それで人里離れた地にて刀を振るっている。
俺には刀しかなく、刀では死んで行った彼らを鎮魂する事ができそうにない。基本的な矛盾を解消できていないまま、修行は三日目の朝を迎えていた。
滝の水が溜まって出来た池に全身を浸す。冷たい水が目を覚まさせてくれる。
俺は池から出て、下履きだけを身に着けた。
刀を手に取り、素振りを始める。雑念を捨て、ただ無心に振る。
敵のことも、味方のことも、雑事を全て捨て去らないと、悟りは掴めないのではないかと思っていた。
ただただ刀を振り、体を痛めつける。どれだけ刀を振っても、心の痛みは消えず、「なぜ」という疑問だけが残り続けている。
(なぜ、あの時仲間を救えなかったのか)
(なぜ、俺だけが生き残ったのか)
(なぜ、俺は過信していたのか)
刀を掴む手の平が擦り切れ、柄が血にまみれる。もう振れないと体は叫んでいたが、俺は振り続けた。
やがて腕の方に限界が訪れ、俺は仕方なく刀を鞘に収めた。
池に手の平を漬ける。冷たい水が傷に染みこみ、痛みを伝えてくるが、池の冷たさは段違いで、すぐに麻痺して痛みを伝えなくなる。それではだめなのだ。
俺は手を水から引き抜いて、水を振り払った。
鈍い痛みの残る手を柄に持っていった時、背後に何かの気配を感じた。素早く刀を抜いて振り返る。
そこには、白い短衣に朱の紋様も鮮やかな一人の女が立っていた。
朱塗りの手甲、黒い脚絆。一見したところでは戦士ではない。
噂に聞く忍者か?
「お前は、誰だ? こんなところで何をしている?」
山奥から現れた女は、特殊な形の短剣を両腰にたばさんでいた。
俺が振るっている刀と同じく、東方からの伝来品。苦無と呼ばれるものだ。菱形に近い形の、円錐状の短剣。
「あなたこそ、こんなところで何を?」
俺は刀を振ってみせた。立ち去れ、というつもりで。
「お前には関わりあいのないことだ」
女はにっこり笑った。釣り目が細くなる。
「修行してるの?」
なぜかわからないが、その笑顔は猫科の動物を思い起こさせる。
無邪気な顔で鼠を引き裂くような、あの。
「さっきから見てたんだけど、なってないわね」
女はゆっくり近づいて来たが、一挙手一投足の間合いで足を止めた。
俺は気付いていないふりをして池から出た。何かするかされるか、よくはわからないが、足元が水であるより地面の方がいい。
女も間合いを保ったままだ。
「ただ刀を振るうだけで強くなれるの?」
「うるさい。お前に関係ないだろう」
邪念を振り払う修行だ、と言いかけてやめる。邪念は落ちていないし、そもそも邪念を振り払ってどうするつもりなのかは、自分でもわからなかった。
「ふふ、武に疑問を持ったのね」
笑う女。俺は目を合わせなかったが、心を読みとられたらしい。
「だったらどうだと言うんだ」
俺は刀を握る手に力を込めた。女は意に介した様子もない。
「それで? 大方邪念を捨てるとか考えてここに来たの?」
皮肉っぽい調子に俺の我慢も限界に来ていた。
「いい加減にしてもらおう」
刀を抜いて女に向ける。
他人に土足で心に入られることに、怒りが湧いてくる。
女は目を細めた。
「ふふ、いいわよ。わたしを切り裂いて欲を満たしたいのでしょう?」
女が舌なめずりをした。あどけない顔から一転、妖艶な一面を覗かせる。俺は頷きもせず刀を構えた。鞘を片手に持ち、摺り足でゆるゆると間合いを詰める。
女は特に構えるそぶりもない。
俺は、右手に持った刀を体とともに振り出し、下段から女を斬った。
女は一歩下がって刀を避ける。振り出した剣を体で追い、次は横殴りに振るう。これも女は下がって躱した。距離を詰めるべく二歩前に。
女は二歩下がる。焦らすつもりなのだろうか。
俺は剣を引き、飛び込む為に体をわずかに屈めた。そこへ女が素早く間合いを詰めて来る。俺は握った鞘を牽制の為に振るが、女は身を低く踏み込んでいるため空を切った。女の体が俺の左脇の下にある。
俺は唸って足を後ろに送った。下がらなければ刀が振れない。
女は下がる俺が振り回す刀の軌跡を読みながら、ぴたりと寄り添って来る。
俺は焦って左手を振り回した。鞘を振り回すことで、体が開き、バランスが崩れた。女の手が軽く脇腹に触れた途端、重い衝撃が俺を襲い、直後の足払いとあいまって俺はあっけなくひっくり返った。
「その程度なの? あなたの武は?」
女は俺の両手首を両足で踏んで見下ろし、嘲笑した。悔しさが頭に血流となって上るが、反撃しようにも両手は押さえられている。俺は脚を持ち上げて蹴ろうとしたが、そう動く前に女は飛んで離れた。
「もう一回よ」
女は今度は苦無を抜いた。
俺は今度こそ、と思いながら刀を振るう。
1分後には、また空を眺めて地面に寝ころんでいた。
そんなことを何度繰り返しただろうか。
俺は女の動きを真似ながら、刀を素早く小さく振ることを覚えた。
歩く動き、相手の剣先、そういったものが生み出す次の動作を、小さな挙動から見覚え、すぐには懐に入られないようになって来た。
「いい顔になってきたわよ、あなた」
女が相変わらず嘲笑を漏らしながら、肉薄してくる。が、恐らくそれは偽の動き。狙いはこちらの足だ。俺は挑発に乗らず、下がりつつ相手の出足を刀で狙った。苦無が剣を流す。またしても見切られた。刀を引き戻そうとする。
「ダメ、狙っている方を見ないでやるの、出足払いは」
女はにこやかに刀の平を蹴る。衝撃が伝わり、俺は体勢を崩した。
開いた体に制することの出来ない空間が開き、そこに女の体がするりと入り込んできた。
体当たりによる重い衝撃と共に俺は倒され、また空を見上げることになった。
「ちょっとはわかったのかと思ったんだけどね」
女は、地面に寝た俺に覆い被さり、俺の体を全身で抑え込んだ。
裸の俺を押さえつけているのは、薄衣の下の豊かな体。俺の体で押しつぶされる柔らかい二つの乳房。汗の浮いた額に、ほつれた前髪が艶めかしい。俺の首筋に女の突きつける短剣がなければ、男女が睦み合っているように見えなくもないだろう。
「やる気を見せて欲しいものね」
女は舌でぺろりと唇を舐めた。扇情的だが、凄惨な笑み。俺はその笑みと女の身体の柔らかさに、全身が痺れたような感覚を味わっていた。
俺の変化を感じ取ったのか、俺が動く前に女は身軽く飛んで離れた。
「今はここまでね」
女は岩陰に姿を消したが、俺はしばらく地面に寝たまま動けなかった。
何が目的でこんなことをするのか。単なる嫌がらせにしては手が込みすぎている。神仙狐狸の類かとも思ったが、肉のある身なのは今の攻防でよくわかる。人の技の範疇で、俺は倒されているのだ。
それに、女の手練れの技に徐々に自分の身体が慣れていくのもわかる。
猛攻に雑念を持つ余裕すらなく刀を振り回していることも。
これが武だというのか? だとしたら、自分に備わっていた武とは桁違いの密度の武を女は備えている。この女はなぜ戦場でこれを使わないのだろう。
俺は考え続けた。
水音が聞こえる。女が池に飛び込んだのだろう。
俺はのろのろと身体を持ち上げた。陽は既に中天高く、汗に濡れた下履きが乾き始めている。
俺はねぐらにしている木の陰に戻る。池の半分ほどを俯瞰できる場所だ。俺は荷物から干し肉を取り出し、木にもたれて座り込んだ。
歯で喰いちぎって咀嚼する。
眼下に陽を反射してきらきら輝く緑の水面がある。水面下、白い大きな影が滑らかに通り過ぎていくのが見える。あの女が泳いでいる。
やがて、女の首から上が水面に出た。女の顔は逆光で見えないが、ダークブロンドの髪が一瞬だけ鮮やかな光彩を作り出す。
さっき触れていた身体の感触とあわせて、あの女の裸身を想像した自分に苦笑する。邪念から逃れて悟りを得ようとしたのに、思いが辿り着くところは邪念ばかりだ。
俺は目を閉じて森と水の音に耳を澄ませた。自分の身体の立てるいくつかの音はいつしか世界の音に紛れて消えていく。
女の立てる音は聞こえてこない。
「こら、何寝てるの。修行じゃなかったの?」
いきなり至近距離で女の声がした。気配などまるでしなかった。
俺は目を開けて女を見た。先ほどの衣装を身に纏っているが、一つだけ違うのは水に濡れた髪。濡れた髪を大きめの布で包んで、大きめの釣り目ををきらきらさせてこっちを見ている。
「心気を養っているとでも言うつもり?」
「いいや、そう大層なことを言うつもりはない」
俺は手に持っていた干し肉のかけらを女に放った。肉を追って立ち上がりながら刀を鞘走らせる。受け取るところを斬ってやるつもりで刀を振るったのだが、女は飛びすさりながら苦無を投げて間合いに入って来なかった。髪から布を剥ぎ取りつつ投げた苦無は、干し肉のかけらを的確に木に縫いつけた。
「ちょっとは油断してるかと思ったんだが」
「いい度胸してるわね」
女は笑った。笑うとなかなか可愛い顔をしているな、と刀を青眼に構えながら思う。
「教えてあげるわ、予備動作が大きすぎる。それに、意念が身体の動きより先に来てるから避けられやすい」
女は顔をしかめた。
「意念を殺す修練をしろとは言わないけど、それならもっと早く刀を振りなさい」
俺は間合いを詰めて刀を振った。女は刀が振り下ろされる前にもう側面に移動している。俺は摺り足で一歩詰めた。今なら女の武器は苦無一本だろうと踏んだ為だ。だが次の一手を決めかねて、ほんの少し刀を振るうのが遅れた。女はまた刀の軌跡から少しだけ距離を取って避け、刀持つ手に蹴りを入れてきた。
俺はその足を嫌って刀を引く。中途半端な振りからなので続けて連撃を繰り出せない。女は回り込んでくる。俺は瞬間迷った。
体ごと下がる選択をする。
女は追撃して来ず、木の横に立って苦無を引き抜き、干し肉を手に入れた。
「今の引き方はいいわ。次の手が不利になることを嫌った動きだけど、次のこと、更にまた次の次のことまで考えて、自分が不利にならないことは大事なことよ」
女は苦無で干し肉を引き裂いた。
「だけど、わたしの狙いがまだ読めてない。だから次の次を読んでの手が打てない」
一片の干し肉が女の口に消えた。
俺は刀を構えているが、打ち込めない。
横に薙ぎ払えば、木を盾に逃げられることが目に見える。横打ちを嫌って縦に切り裂こうとすれば、おそらく刀の峰を踏まれる。
ならどうすれば?
「どうすればいいかは教えてあげない」
女は干し肉を噛みながら言った。また心を読まれた。
俺は逡巡した後、下段からの擦り上げ打ちを選択、また軽く下がられた。
「半分正解。でもそのやり方は敵を逃がすわ」
女はじわり前に出てきた。俺は刀を振り回そうとして思いとどまった。
木に当たってしまう。下がるしかない。
仕方なく女の速度にあわせて下がり、刀を構える。
「そう、地の利を得て戦うことも大事」
ゆるゆると前進してくる女に対峙しながら、俺もじわじわ下がる。
刀が障害物に当たらずに振り回せる間合いが取れたら、仕掛けるつもりだった。が、その前に女が突進してきた。
俺は下がりきれず、またしても懐に入られた。この距離で打つ手がないことは経験済みだ。俺は体を捻って女の一撃を防ごうとし、不安定になったところを突かれた。
視界の中の空が一回転する。
「意念が出過ぎてるわ。自分に有利な場所に来るまで待ってやる、って。相手に読まれないようにするにはどうするか考えることね」
女は地面に転がった俺を眺めて言い放った。
俺は半身を起こしたが、女はやる気を失ったようだった。
「鎧もなしでその状態じゃどうしようもないわね。大方、鎧に頼って突進したりしてたんでしょ。それで武を語るなんて、十年は早いんじゃない?」
俺は言い返す言葉をもたなかった。その通りだったことを恥じて。
「その通りだ・・・少し一人にしてくれないか」
「そうね。考えるといいわ」
女は残った干し肉を俺に投げつけ、歩いて離れて行った。
その背中が、肩を落としていたように見えたのは気のせいだったろうか。
俺は干し肉を食べ終えると、水辺に立って朝からの修行を思い返してみた。
女はしっかり俺の隙をついて効果の高い攻撃を入れてきていた。
俺はと言えば、先を読むことができず、女の攻撃に対しての場当たり的な対処しか出来ていなかった。
斬ろうという意志が見える、と女は言った。
斬る意識なしに斬れるわけがない、と俺は思っていたが、そこに女の意見とのずれがあり、疑問があることが朝からの修行で見えてきていた。
意念? 言っている意味はわかる。そんなものが見えたら苦労しないのではないか。全ての意念が見えれば、攻撃を回避することは実に容易い。
ただ、俺は朝から女に当てるつもりで振って、一度も当てられなかった。
意念を読むというのは達人の技なのかもしれない。
だとしたら、考えてもそれを身につけることは出来ないだろう。
流した汗と血がおそらくそれを可能にする。俺は未熟だ。
だが、斬ろうとする意念・意志など、実は見られてもかまわないのではないか。見られたとしても見切られない早い攻撃ならば、意念が見えようが見えまいが関係がない。恐らく、その早い攻撃を体に覚え込ませることで、見切られない攻撃が常に出せれば、結果として意念が見えなくでも平気になる、ということなのではないか?
意念・意志が見えるということに関する推論は推論として措いておくとして、早急に必要なのは斬撃の速度を上げること。
それを極めて行けば自ずから見えるようになるだろう。
俺は深呼吸しながらそう結論付けた。これは女の言ったことと一致する。
恐らくはそれが正しいことだ。汗を流すのだ。
素振りの仕方を工夫する必要がある。俺は水面に向かって剣を構えて鋭く早く刀を振るってみた。習い覚えた技に、頭の中で修正を加えながら振り始める。
型を振りながらその次のことを考える。
更に必要なこととして、斬った後にすぐに退くことが必要だと思い知らされていた。相手に合わせ、しかも合わせた後の振り抜きから次の構えに遷移、次の攻撃に合わせる・・・この繰り返し。
これができなければ、身軽な女を斬ることなど出来ない。俺は今まで、斬るためには踏み込んで斬らなければならない、であるとか、大きく後ろに刀を引いて、加速度を付けて斬らなければ致命の攻撃にはならない、とそう思いこんでいた。
つまり、斬ることを意識するから大きく振らなければならない。
これは俺の誤りだ。
手数を多くして相手を崩さなければ致命の攻撃など出せようはずもない。一撃必殺・・・言葉の聞こえはいいが、それは余程の実力差があってのことだ。今の俺と女の間の差。
俺に剣術の手ほどきをしてくれた師は何と言っていたか。目を閉じ思い起こしてみる。久しく忘れていた言葉が心の中に甦る。
『始めに開展を求め、後に緊湊に至る』
秘訣の言葉の意味が今ならわかる。大振りをしていたのでは隙が見えてしまう、ということだったのか。刀を振るう速度が遅くては当てることすらできない。緊湊、つまり小さく早く振って威力のある攻撃にしなければならないのだ。
ようやく俺は次の段階に進むことが出来るようになったらしい。その段階が出来て、初めて斬撃を連撃に、効果のある攻撃とすることが出来る。
俺は小さなものではあるが、目標を見出して心の重荷が少し軽くなったことを感じた。遠い空の師に心で感謝を捧げる。
そして、女に畏怖を感じた。
師と同じことを言い、実践し、しかも強い。
これほどに強い者が、なぜ戦場で目立たなかったのだろう。
「世界とは・・・これほどまでに広いのか」
思わず独り言が口をついて出た。自分の矮小さを認識する。
師匠より伝授された技を、一から全て浚ってみよう。
そう思った。
俺は思考の整理と素振りを何度となく繰り返したあと、女の消えた方向に足を向けた。
女は水辺にしゃがんで何かを見ている。両手で何かを包むようにして。その横顔は物憂げで、はっとするほどの美を秘めている。
「先生」
俺は刀をしまい、一礼した。
「一手ご教授をお願いしたい」
女は手を体側に戻した。手で包んでいたのは、すらっとした葉茎を持つ白い水仙。風に揺れる細いその姿が女と被って見える。
「買いかぶらないで。先生と呼ばれるほどの技量はないわ」
女はそう言うと、苦無を構えた。
俺も刀を鞘走らせる。鞘はいつも通り左手で引き抜いて構える。
教えを請う側の礼儀として、俺から仕掛けた。距離を詰める。
可能な限り小さく早い斬撃を水辺の女に仕掛けてみる。
女が僅かに下がった瞬間、刀が空気を切り裂き、一瞬刀身から炎が溢れた。女の白い胴衣に火の粉が飛ぶ。
「本気ね」
女が嬉しそうに言った。赤い舌がくちびるをちろっと舐める。
俺は自分が放ったものが信じられなかった。火剣の技など、伝説の英雄が使ったと語られる武技だと思っていたからだ。
俺は強くなったのかもしれない。そんな思いを噛みしめる暇もなく、次の斬撃を繰り出すべく足を前に。と、その出足に女が合わせて蹴ってくると≪読めた≫。足を後ろに下げながら斬り下ろす。女は蹴りを途中で断念した、と≪読めた≫。
斬り下ろした刀を右下段からの構えにし、次の出方を考える。
女は一歩下がって嗤った。
「大層な進歩じゃない? この短時間で意念を読むことを覚えたなんて」
そうか、これが意念を読むということなのか。
「剣を交えるということは、相手を知るということ。今のあなたにならわかるでしょう」
女の言葉に頷く。そうだ、わかる。今のお前の動きが偽物でなく、蹴りたかったのだが斬撃の早さに退いたのだと。
「だけど、それだけが出来てもダメ。教えてあげる」
女は苦無を体に隠して体を低くして突っ込んできた。
下段からの擦り上げの太刀・・・間に合わない! この女なら刀の軌道を軽くかわすことが出来るだろう。それほどに単純な軌跡しか織り出せない。俺は刀を振るわず、右後方へ飛び退いた。
空中で刀を体側に持って行き、横殴りの斬撃を用意。
女は追随してきた。俺は着地と同時に刀を横へ振り、女に刀を捉えられぬよう下段へと斬った。女は刀の間合いを寸前で見切っている、今朝の俺ならばそこで刀を踏まれていただろう。
俺は腰を左から右に捻って下段から体の中心にまで刀を引き戻した。青眼に戻る。女は刀を避けて左側面へ回り込む。
俺は左足を引いて回転し、女を正面に捉え続けようとする。
≪甘いわ≫
そう聞こえた気がした。女は体を低くして下段の回し蹴りを繰り出していた。青眼からの斬り方ではそれを捉えることができない。俺は右足を刈られ、また空を仰ぐ羽目になった。
倒れた俺を女が覗き込む。
「左側は斬りにくいでしょ。それと接近されるのを嫌いすぎ」
その通りだ。俺は言葉を発せなかった。
「だけど進歩はしてる。なぜ後ろに下がろうとしたのか、よく考えてみることね」
女は離れて行った。
相手に合わせて動くとどうしても遅くなる。遅くなることが次の手の遅さを招く。であるなら、相手が動く瞬間、相手よりも先に動くか、相手の動きの先の先を見切り、意図した攻撃を挫くより他はない。これは一見不可能なことに見えるが、意念を感じとれるならば、もしかして・・・
思考の迷路に落ち、しばらく寝転がって空を見ていると、どんよりとした雲が西の空から現れ、見る間に天蓋を覆って行く。
大気に水の匂いが満ち始めていた。
雨が来る。
俺は荷物を纏めると、滝のそばにある岩屋に放り込んだ。
女もどこからか自分の荷物を持って現れ、岩屋に荷物を入れた。
荷物を置いた途端、ぽつぽつと雨が降り始め、すぐに激しい雷雨となった。水面にたくさんのしぶきが現れる。昼日中なのに、辺りはほの暗くなり、清涼な水が木の葉を揺らす。時折稲光と、それに付随する轟きも聞こえてくる。
岩屋と言ってもそれほどは広くない。人が数人入ればそれで一杯になる程度の広さだ。俺と女は左右の壁に分かれて座り、苔むした岩壁に背をもたせかけた。
しばらくは二人とも口を開かなかった。ただ激しい雨音が世界を埋めていた。たまに響く遠雷だけが唯一の異音だった。
ふと気が付くと、女の荷物に緑の長い刀袋がある。錦の紐で口を縛ってある。女は膝を抱えたまま、雨を眺めている。
俺はためらいながら口を開いた。
「なあ・・・なぜ俺に教える気になった?」
女は視線を雨から外さない。長い沈黙が続いたあと、「気まぐれかな」
一言だけ返ってきた。意味を図りかねて、俺も雨に目をやる。
雨はますますひどく降り、森を白い霧のように染めていく。
滝の音よりも雨の音が大きい。
「・・・知ってる人の目に良く似てた」
唐突に女が繋げた。
「そうか。その人も戦士だったのか?」
「死んだわ」
雨は人を追憶に誘うと言う。女は激しく降りしきる雨に、その人とやらの姿を思っているのだろうか。
問わず語りに女は続けた。
「酷い戦争だったわ。お前は来るな、と言い残して彼は出陣していった。後で刀だけ戻ってきたわ」
納得がいった。
「恋人だったのか」
女は肯定も否定もしない。
「その時の目が、そっくりだったわ。今朝あなたが一人刀を振っていた時の目と」
雨も雷も止む気配がない。ひどくなる一方の世界の音響。
「勝手なものね、男は。残される者のことなんか考えもしない。
栄光の内に死ぬことしか考えていないのね」
ぽつりぽつりと呟く言葉に、俺は胸を締め付けられた。
「個人の技をいくら磨いたって、無謀なことをしたら死ぬわ。
わかっていても死地に赴くのが武人なんだって。馬鹿よね」
俺は返す言葉もなく雨を見つめていた。自分の行ったことはわかっていても死地に赴くことだった。仲間を失うことより自らの功名心にはやり、自分のための栄光を求めたことだったのだと、理解できたからだ。
「戦争に行くということは死ぬことじゃない。目的を果たして生きて戻らなければ、他の人に何か伝えることも、守った国を見ることもない。
なぜそれがわからないの?
わからないのなら、戦争なんか行かなければいい」
女の言葉はいちいちが重く突き刺さる。
「あなたもそうなの? 今磨いている武は、何のため?」
「俺は・・・」
俺は乾いた唇を舐めた。
「俺は、戦争に出ることで認められるんじゃないか、と思っていた。敵を倒し、武功をあげて、いっぱしの武人と認められることを夢見ていた」
女は依然外を見ていたが、聞いていることは間違いない。
「俺はその功名心のせいで仲間を失った。自分にもう少し強さがあれば仲間を失わなくて済んだのかもしれない、と思っていたが、それは最初から間違っていたんだな」
女の表情が少し動いた。張りつめていた空気が緩んだのを肌で感じる。意念を感じとるというのは、こういうことがわかるようになるということなのだろうか。
俺は嘘のない素直な気持ちを伝えた。
「俺は、今教えて貰っていることを、自分の功名心の為には決して使わないと約束する。仲間を守り、生き延びるために最善を尽くし、その為に使う。いのちを守り、悲しむ者が少なくなることを目指す。武とは、盾だ」
それが、死んでいった仲間に対する俺なりの鎮魂になるとそう思えた。生き残った俺の義務なのだと。
女はちらっと俺を見て、長いため息を吐いた。いくつかの 感情がその瞳を通り過ぎたように思えたが、未熟な俺には全てを解読することはできなかった。
「その言葉を口にするにはまだ、あなたには足りないものがあるわ」
女は静かに言った。
「だけど、信じてみてもいい。・・・そう思える」
その言葉を最後に、女は雨が止むまで口を開かなかった。
「ノベル-AT通信-」作者と作品一覧
- 作者
- 作風
- 作品
※文章を閲覧される場合は、サムネイル画像をクリックして下さい。