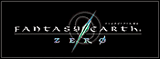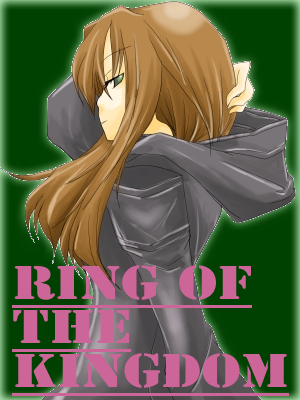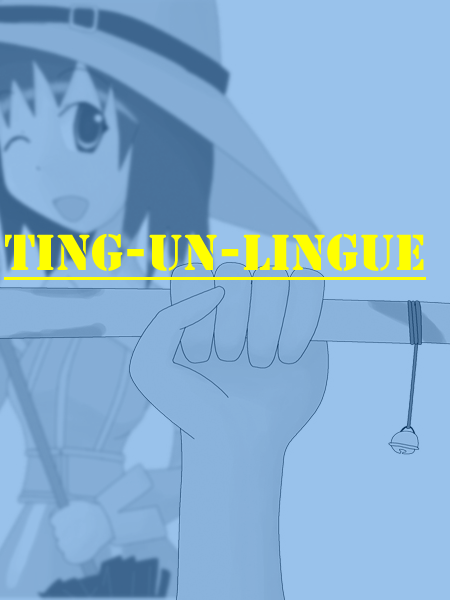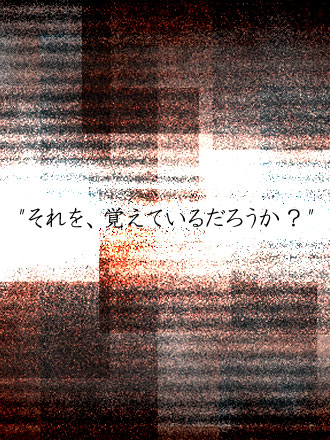About "AT通信"
- FEZ内であまり役に立たない情報を、自分達が楽しみながら発信していく「組織」、またはその「情報媒体」です。
POWER PUSH EVENT
PICK UP
NOVEL
「War Dogs」---著[Anly]---画[ちるね]---
第三項
翌日。相変わらずの日暮れ空。
「…おい、クロム」
「……あ、な、なに?」
斧を振り上げる手を止め、呼び声に応える。
横目に見ると、うんざり顔のフェルがいた。
「おめぇ、後、何回よ」
「あ、えと…ちょうど、八〇〇、かな」
今日の本数は千と五百。
先生が僕に、というか、新兵のみんなに与えた素振り命令だ。
昨日と違い、オベリスクの破壊訓練はなかったけども。
「…まだ半分いってねぇか…こっち後、九〇〇くらいだわ」
差は一〇〇本。
多いのか、少ないのか…いや、多いんだろうけど、あまり実感がない。
まき割りなら、ほんのちょっとの違いしかないけども…同じ斧を使う動きでも、全身に力で振り込むスマッシュは、やっぱり疲れるや。
「そ、そう」
返事につまる。
フェルは何が言いたいんだろう…数の確認なんて、わざわざ聞くようなものじゃないと思うんだけどな。
自分の数は、自分で数える。それだけだし。
七九九、七九八。
素振りを再開し、頭の裏で数を数える。
昨日今日と、斧を振りっぱなしな腕が痛いや。
手のひらにもマメが出来てたし、そのうち潰れて血豆になるのかと思うと、少し気が落ちる。
あれ、痛いんだよなぁ…。
でも、先生の命令だし、やめるわけにはいかない。
七九七、七九六。
腕が腫れたら、引くまで休んで、またやればいいんだし。血豆になって潰れても、斧が握れるなら続ければいい。
素振りに時間制限はなかったから、どれだけかかっても、やり遂げよう。
そう、思う。
「…ほんと、マメなやつ」
フェルの呆れた声。
「ま、どうでもいいか。人それぞれってなもんだ」
と思えば、からっとした声に。
まきをまっすぐに割れた時みたいに、なんだかすかっとするのがフェルのにおいだ。
きっと、そういうヒトなんだろう。
「あ、らよっ、とー!」
豪腕一閃。
土煙を巻き上げていくフェルのスマッシュは、ほんと、見ていて爽快だ。
見ている場合じゃないのは分かってるんだけども…あまりにも、僕の理想すぎて、いやになる。
力強く振り上げられた斧が、ぴたりと止められ、身体の軸もぶれたりしない安定感。
僕には、絶対にマネできない。
「すごい…」
「あん?」
あ、まずった。
「あ、や、な、なんでも、ない、…です」
うっかりこぼした言葉をごまかす。…無理があるけど。
「ふーん? ま、どうでもいいや」
それきり何も言ってこず、フェルはまた素振りに戻っていた。
ほっとしたような、助かったような…よく分からない気持ちだ。
※
翌日のこと。今日も空は暗く、寒い。
「…やってらんねぇ」
誰かがぼそりと呟いた。
声には嫌そうな臭いがありありとしていて、心底からそう思っているようだった。
「ただの素振りで、二千本? 今日も素振りだけで終われってのか?」
昨日、一昨日。
初日こそ、オベリスクの破壊訓練があったものの、あとはずっとみんな、スマッシュの素振りだけをして過ごしていた。
「おかしくね? 他のやつらは、もう少数連携とかやってるらしいぜ? なんで俺らは素振りなんだ?」
先生が言ってるから、じゃないのかな。
周りのみんなの臭いからは、どうも違うようだけど。
よく、分からないや。
一三八〇、一三七九。
さすがに連日とになると、手とか腕だけじゃなく、指もそうだし、身体も、腰も、足とかもぱんぱんに腫れて、痛い。
さっき心配してたマメも潰れて、いまじゃ立派な血豆ができてるし。
…あ、そうか。この古斧の柄巻き、みんな血豆で染まってるんだ。
これまで、何人くらい、何回くらい振られてきたんだろうな…僕も、その一人になってるのかな。
少しだけ、うれしいことを見つけた気がした。
一三七八。一三七七。
ゆっくりでもいい、確実に、形を気にしながら身を入れて打ち込もう。
気をそらしたままやると、ケガをしたり失敗しやすいのは分かってる。
ましてや扱うのは戦仕立ての古戦斧…まき割りに使ってた手斧とは、大きさも重さも、危なさも段違いだ。
うっかり転びました、で頭や腹を割ってもおかしくない。
…武器。戦争で、ヒトを殺すための。壊すための、モノ。
怖い反面、どこか惹かれる気もするな。
「聞いたか? 狂犬ペールんとこに付いた連中、もうじき実戦投入されるらしいぜ?」
「それ、良いことか? ていのいい捨て駒くせーのがぷんぷんするんだが」
「特攻バカのとこだし、どうせ脳みそまで筋肉になってるような連中だろ。ほっとけよ」
「でもよ…実戦だぜ?」
しん、と静まり返るみんな。
なんとなく、静かにしないといけない気がした。
ちらりと横に居たフェルを盗み見ると、どこか遠くを眺めるような目をしている。
「…そりゃあの、ダルクの騎士んとこに付けたまでは良かったけどよ。…他んとこの奴らに聞いてみた話、他はもっとこう、実戦的なことやってるらしいぜ」
「てーと?」
「片手とか、両手のコンビでやったり、両方使える訓練をやったり。魔術師を呼んで、前線での動き方をやったり、まぁいろいろだな」
「すげーな…本格的じゃねーか」
「ああ。万年、兵力不足なお国柄、俺ら傭兵を早く一人前にしてーんだろな。あんましアテにされてもうざったくなるが、少なくとも…コレよかましだと思うぜ」
気の抜けたスマッシュが一つ振り上げられた。
「…正直な所、お前らもどうよ? このまま、あの女の言うこと聞いておくつもりか?」
あの女…先生のことかな。
…なんだろう。すごく、腹が立つ。…なんだろ。
「…なんだよ、クロム坊。何、睨んでんだテメェ」
…にらんでるのだろうか。よく、わからない。
ただ、無性に、目が熱いけども。
「………」
「けっ。しゃばくせぇ小僧がいきりやがって。やってらんねーな…」
ドサ、と。
持っていた斧を無造作に投げ捨て、立ち去る新兵の誰か。
「俺、抜けて他いくわ。あばよ」
「あ、おい待てよ! ケディス!」
慌てた様子で付いていくのも、何人か。
フェルは、相変わらず遠くを眺めていて…どうでも良さそうなにおいがしていた。
ふと、不安になって先生の姿を求め、近く遠くに目を凝らす。
…いた。
先生は、いつもように、素振り場となっていた小高い丘の下で、いつものように佇んでいる。
僕らを見張るでもなく、見守るでもなく、見上げるでもなく。
どうでも良さそうな、無関心で冷たい匂いをしたまま、まぶたを伏せて。
まるで氷でできた、女神様の彫像みたいに…離れていく新兵たちを捨ておいた。
「ノベル-AT通信-」作者と作品一覧
- 作者
- 作風
- 作品
※文章を閲覧される場合は、サムネイル画像をクリックして下さい。