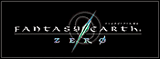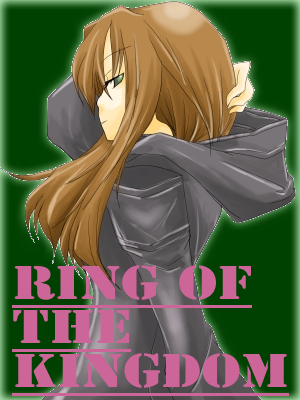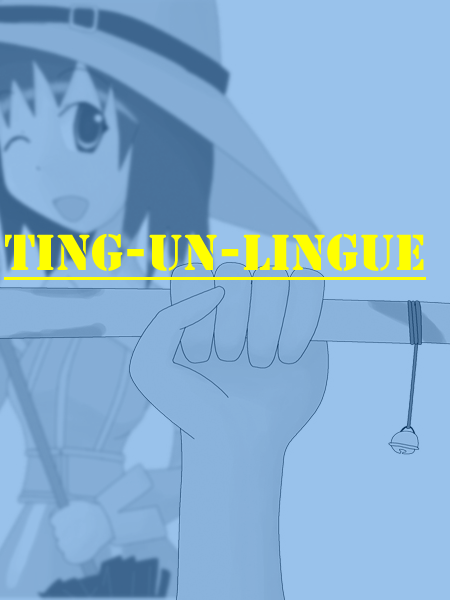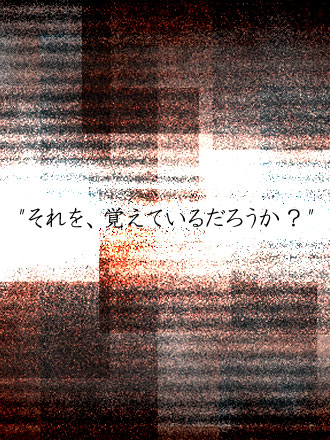About "AT通信"
- FEZ内であまり役に立たない情報を、自分達が楽しみながら発信していく「組織」、またはその「情報媒体」です。
POWER PUSH EVENT
PICK UP
NOVEL
「ペールライフ」---著[Anly]---画[ちるね&みかん]---
第三項(完)
『静かの森』の一階部分、フロアの片隅。
ロウソクの灯りが頼りない中、適当なソファに腰掛け、相棒をぞんざいに床に捨て置く。
ごろんと重い音を立て、それを物言わぬ抗議とした相棒を足蹴に、飲食に邪魔な手甲だけを外しに掛かる。
防具の造りは、単純なほど信用できる。
ごちゃごちゃとした飾りや、登坂用のつかみ、急ごしらえの簡易盾など、余計な機能はないに限る。
手甲は剣が握れ、敵兵を殴り倒す程度のことができればいい。
いっそのこと、何をつけないでも構わないくらいだ。
が、実戦では予測外の乱立が当たり前、飛び石一つがどうなるか分からぬ以上、最低限の保護だけはやっておいても損はない。
その点、魔獣の皮を剥いでこしらえた革手甲は、申し分のない扱いやすさではあった。
「はい、お待たせ」
「すまんな」
差し出されたぼんの上に乗っていた物を手掴みする。
食事の礼法作法、行儀など知ったことではない。
レッセンの用意してきた物は、瓶詰めの赤いブドウ酒と、ベーコンの切り身をパンに挟んだだけの簡易食。
「…大丈夫?」
「ん?」
「いえ、来るとき、痛そうだったから…」
「ああ…もう慣れた」
人間の慣れとは恐ろしくもあり、うまく出来ているものである。
身を砕くような痛みでさえも、じきに慣れるのだ。
「…今度は、どんな戦争だったの?」
「別に、話すほどのものじゃないさ」
たかが一対五十、ただの負け戦。酒の肴にもなりはしない。
そんなものを得意げに、あるいは捻じ曲げて語るほど落ちぶれてはいない。
パンを一口にかじり、ブドウ酒で流し込む。
不味くはないのが、この宿のいい所か。
特にこれといって味にこだわりなんぞ持っちゃいないが、不味いよりは美味い方がいいものだ。
近年は食材の劣化、悪化、低質化が著しいといった環境を考えると、不味くならないだけでも大したものか。
平然と毒入りの肉を出す店や、腐りかけの香草を混ぜる所もあるのに、ここはそうじゃない。
首都でも数少ない、くつろげる宿である。
「ウソ。…マネージャーが、二対五十になってます、とか叫んでました」
「それが?」
アドリアか、あるいはフランチェスカか。
どちらにせよ、余計なことをしてくれるものだ。
「アベル、アンバーステップ、タマライア。中央でもキンカッシュとウェンズディで戦争中だ。いまも」
中央大陸のみならず、隣国のネツワァル、ゲブランドからの本土侵攻がなされている。
元々、兵の数が少ないカセドリア王国に雇われた傭兵である以上、戦争には駆けつけねばならない。
正規兵やまっとうな兵では対処しきれない、負け濃厚の戦いにこそ傭兵は赴くべきだからだ。
でなくば、傭兵の価値が失せ消える。
「一端の兵どもでも対処に困るほど、戦場は溢れているんだ。多少の特例があっても、おかしくはないだろう」
何のための傭兵か。何のために、好き好んで戦いに明け暮れるのか。
まっとうな兵ではいられないからこその傭兵、金で雇われ命を削るだけのならず者。
戦わずして、どうしろというのか。
「でも」
なおも続けようとしたのを目で制し、残りのブドウ酒を飲み干す。
休憩は終わり、また次の戦争が待っている。
「厄介になった。ツケは朝、リングで倍返しする」
傭兵にとって金は命。はした金の二束三文で戦争に赴くほど、金には価値がある。
反し、戦争の結果に応じて支払われるリングという、軍隊特有の通貨。
主に強化武具や防具、上級素材や道具を購入する際に必要とされる物だが…俺には必要ない。
が、どうも世間では金よりもリングの方に価値があるらしい。
よって、不要なリングで飲み食いし、ツケの返済に充てる分には都合がいいものだ。
「…うん。けど、ちゃんと帰ってきてくださいね?」
「不帰還を成就させた時は、喜んでウィンにたかればいい。野郎のことだ、たんまり持ってやがるはずだからな」
何せ、連合諸王国としてのカセドリアを率いる軍参謀様だ。
エルフの小娘をたぶらかし、何某かの財宝を掠め取っていてもおかしくはない。
「…まだ、あの人の後を追おうとしてるのですか?」
「ああ」
「…どうしてですか? 何故、そんなに死にたがるのですか?」
多少のしつこさを疎ましく思うが、美味いブドウ酒を飲ませてもらった。
それなりの受け答えに付き合う程度の時間は、まだあるか。
「戦死こそ誉れだから、だな。傭兵にとって、それ以上の名誉はないんだ」
戦い、死ぬ。
戦場で、敵の刃にかかって散ること。
当たり前のはずが、当たり前にならないこの世界において、闘いの果てに待つ死は奇跡とも言えよう。
“戦場では兵が死なない”
――そんなバカげたシステムの枷、クリスタルの恩恵などくそくらえだ。
故に、真っ当に戦い、真っ当に死ぬ。
それだけが、俺の願いなのだ。
「…おかしいよ、ペール君は」
「そうだな」
否定するつもりは毛ほどもない。
死にたがりの狂人など、連合の傭兵では珍しくもないだろう。
「…やっぱり、あの人の…アーチャーの影響、なのかな…」
「かもしれんな」
その名を知らぬ傭兵は、カセドリアに存在してはならない。
建国の英雄として表に出たウィンビーンなどとは別格、別次元の英雄。
俺たち『森』の傭兵が目指すべき理想、切望する最期…戦いの最中での死に様は、強烈に焼きついている。
皆が皆そろって、ああなりたいと願い、その後を追うのも無理はない。
それほどまでに、戦場のシステムを覆したアーチャーの死は印象的だった。
「…戦争、いつまで続くのでしょうか」
「さてな」
この戦乱、収まる気配はない。
戦いが戦いを呼び、勝敗は憎しみと絆を生み出し、また新たな闘争が巻き起こる。
その繰り返しがこの世の歴史である以上、これまでも、恐らくはこれからも、戦争は終わらないだろう。
戦争が無くならない限り、傭兵もまた不滅。
俺のような輩には、ちょうどいい時代であるとも言えよう。
「では行ってくる。美味い酒だった」
空瓶を空け返して席を立ち、足蹴にしたままだった相棒を担ぎ直す。
背ほどもある大剣も、戦がなければただの鉄くれ。
俺と同じ。
革手甲をはめ直し、ぐっと力をこめて拳を握る。
まだあちこちの痛みは拭えないが、動けないほどでもない。
この分ならば、戦場につく頃には大分ましになっているだろう。
十分すぎるほど、くつろげた。
「…少し、待ってくださる?」
「ん?」
宿を出ようとした所、待ったがかかる。
何かとレッセンに向き直ると、何やら小さな包みを持っていた。
「これを」
「これは?」
差し出された小包みを受け取り、軽く縦に振ってみる。
特に何の変哲もない、軽い小物のようだが。
「…常日頃、日夜を構わず戦い、国を守って頂いている御礼…です」
「食えるものか?」
「はい、それなりには」
「ならば頂こう」
この程度の大きさなら、向こうに行っての待機中にでもつまめるだろう。
手持ち無沙汰にならない気遣い、たまには有難く思っておくのも悪くない。
「生きて、帰って来てくださいね」
物憂げなレッセンの言葉。
生還を約す、切なる願いか。
俺には、何も返す言葉がない。
肩をすくめる仕草を返事とし、踵を返して宿を出る。
次の戦争に向かうため、新たな敗北を得るため。いつか散り往く、そのために。
「この戦争は、いつまで続くのかな…」
耳に残る、彼女の言葉は遠く――
「ノベル-AT通信-」作者と作品一覧
- 作者
- 作風
- 作品
※文章を閲覧される場合は、サムネイル画像をクリックして下さい。